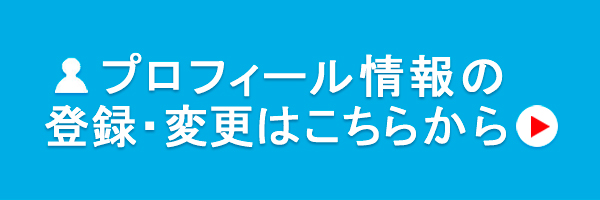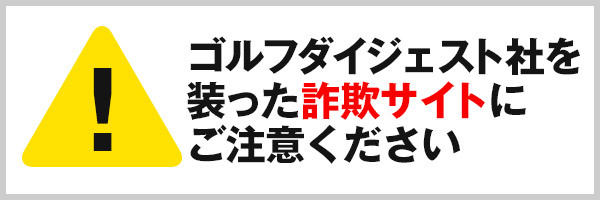【ターニングポイント】深堀圭一郎「たとえ遠回りでも“自分らしさ”を貫きたい」
 ターニングポイント
ターニングポイント
プロゴルファーの一歩は、一人一人異なる。深堀圭一郎は、どれだけ努力してみても、同世代の仲間たちからは遅れてしまう一歩だった。人とは違った一歩でも、またそれが遠回りでも、彼は「自分らしさ」を貫き、頂点を目指し続けた。日本オープン最終日、5打差を追いかける、その朝に迎えた、ターニングポイント──。
TEXT/Yuzuru Hirayama PHOTO/Hiroaki Arihara THANKS/サウスゴルフアカデミー(SGA)品川サロン

「与えられるものを
詰め込みすぎて
自分から崩れていった」
忘れられない誰かの言葉がある。
深堀圭一郎の場合、父・孝から教わった言葉だった。「自分らしさ」とはいかに作ってゆくものか。体が小さく、細く、弱くても、錚々(そうそう)たる顔ぶれを一歩後ろから追いかけ続けたジュニア時代。そのひたむきさ、粘り強さに、大成してゆく彼の、ゴルフの原点がある。
煎餅の製造業を営んでいた父の孝は、ゴルフ愛が僕より100倍もあるような人でした。僕の最も古い記憶は、アメリカから取り寄せてくれたプラスチックのゴルフクラブとボールで遊んでいたことです。地面の土の隙間にティーアップして、ベレー帽をかぶってね。
東京の実家は幹線道路沿いにあって、当時は空気が汚れていたようでした。野球とゴルフを両立していたのですが、父は体が弱かった僕に、自然の中でいい空気が吸えるゴルフをやらせたかったのかな。
中学1年生になる前の3月、初めて試合に出場しました。その東日本ジュニアで、今でも仲がいい丸山茂樹や伊澤利光さんたちと出会ったんです。練習場には大人ばかりだったので、こんなにゴルフをしている子どもが大勢いるんだと驚きました。それと同時に、丸山や伊澤さんの上手さにも。
そうした仲間と、春と夏しかない試合のたびに、自分がどれだけ成長できたのかを確かめることが、楽しみであり、不安でもあり。僕は体が小さくて細くて弱かったので、人よりも一歩遅れてもいいから、着実に基礎を作ろうと思っていました。予選落ちするたびに悔しい思いもたくさんして、でも人と比べるより、自分に足りない技術を必死に埋めていくことだと。
ショートゲームや、瞬時に状況判断する対応力は、当時から僕の武器でした。一人でバスを乗り継いで練習場へ行き、70ヤードしかなくても、広いコースを想像して球を打っていました。家の中でも、くしゃくしゃにしたバスタオルの上でバンカー練習(笑)。明大中野高校2年時に日本ジュニアに優勝できたときには、僕でもこんな位置まで来られたんだなって、みんなに追いつけたようで嬉しかったです。
高校3年生でナショナルチームの第1期生として選ばれ、そのあたりでスウィングを崩しました。当時は様々な人たちの助言をすべて受け入れてしまって。向き不向きを取捨選択できる能力がなく、与えられるものを詰め込みすぎて自分から崩れていったんです。そんなとき、幼い頃から教わってきた父の言葉を思い出しました。「人と同じことを真似るのではなく、自分がいいと思ったことをやり続ける。それがやがて『自分らしさ』になるんだよ」。そんな父の教えは、今でも、確かにその通りだなと思っています。


高校2年で日本ジュニアを制し、ナショナルチームにも選ばれた。だが、さらに上を目指してたくさんのことを習得しようとして失敗。プロテストには受かったが低迷が続いた
「下から上げていって
『これなら打てる』っていう
番手が6番アイアンでした」
ドライバーを打てずにプロになったゴルファーがいるだろうか。
深堀圭一郎は長年ドライバーイップスに苦しんだ。それは今でも完全には抜け切れていないほどの重症だという。けれども、ゴルフというのは人生にも似て、たとえドライバーが打てなくても、致命傷にはならない。できるだけ遠くへ飛ばす、とはまったく逆の発想で、彼はライバルたちの後をゆっくりと、自分らしく追いかける。
明治大学時代は、結局一つもタイトルに手が届きませんでした。研修生になってプロを目指したのですが、大学1年生の途中からドライバーイップスになり、それがずっと続きました。実は今も完全には抜け切れてはいないくらいなんです。インパクトで45度に開いて当たってしまうので、それが怖くてトップからクラブが下ろせない。芯には当たるので、右隣のホールのさらに右側のラフから第2打を打つという(笑)。もちろんOBも連発して、試合で88を叩いたこともありました。
プロテストは丸山茂樹と一緒で、僕はドライバーを4日間で一度も握れませんでした。3番ウッドでごまかして、最後のパー5のティーショットは6番アイアン。今でもこの考え方は変わらないんですけど、僕は長いクラブでどこまで遠くへ飛ばせるか、という計算はしないんです。ウェッジからドライバーまで、下から上げていって、自信を持って『これなら打てる』っていう番手が、そのパー5では6番アイアンだったということ。
プロ入り後はジャンボさん(尾崎将司)の全盛期でしたし、プロテストをやっとすり抜けたような僕が活躍できるほど甘くない。そんなとき出会ったのが、TUBEの前田亘輝さんでした。ゴルフをご一緒させていただいたとき、前田さんにはサインを求める人がたくさんいて、丸山茂樹にもいた。「圭ちゃんのところには、今はサインを求める人は来ないけど、この悔しい気持ちを忘れるな」と兄のように励ましてくださって。後日、僕のために『傷だらけのヒーロー』という曲まで作ってくださって。試合で苦しかったとき、心の中でその歌詞をお借りして、自分で自分の背中を押して、もう一歩を踏み出していましたね。
「“臆病深堀”を封じ込めて
日本オープンを制しました」
自身のゴルフ半生を振り返るとき、深堀圭一郎は、これまで多く語ってきた技術論は、もう語らなかった。
むしろ、他者の目には映ることのない、誰にも話したことのない、心の内。日本オープン優勝という、大きな頂に立ってみせたときのことでさえそうだ。重要だったのは、幾万のギャラリーが見つめた芝生の上での出来事より、誰もいない、トイレの個室での、子どもの頃から続けてきた思考こそが、自身の財産だったという。
2003年、日光CCでの日本オープン、最終日7アンダーで5打差を逆転して優勝することができました。それよりずっと以前、子どもの頃からしてきたことなんですけど、あえて難しい局面を思い浮かべるんです。そこでどう打てばいいかを考えて、最後のパッティングを入れて優勝するまでの道筋を頭の中で事前にシミュレーションする。こういうふうに勝てれば、こういう人生が待っていて、こういう家に住める、というところまで。誰かに教わったわけでも、本を読んで知ったわけでもなく、どんなスランプでも好調でも、ずっとやり続けられたのが、僕の財産です。
それはなぜかというと、僕は臆病な人間だからです。すぐに悪いイメージに支配されてしまうので、最初から予行練習をしておく。だから本番で最悪の状況になっても、初めまして、じゃないんです(笑)。毎朝トイレの個室で約10分閉じこもって、技術では負けても、気持ちでは負けないぞと。ビビらずに最後の最後まで振り抜いて、優勝するまでをイメージして、最後に「よし!」と言って、心のスイッチを入れてから、扉を開けて出てくるんです。そうして『臆病深堀』を封じ込めて、日本オープンを制しました。
ラウンド前の考え方がそれなら、ラウンド中は、一球を打ったとき、これを忘れてしまった、と後悔するのをやめること。考えることはすべて思い巡らせて、準備を怠らない。それを徹底すると、クラブを上げた瞬間からは、もう考えることなんてない。つまり、全部の思いを一球一球に込めて打つ。結果は後からついてくるもの。誰かに勝とうということではなく、全球、その準備をやりきれるゴルファーでいること。それが、僕にとっての挑戦なんです。



5打差5位タイから猛追し、逆転勝利!
最終日、出だしの4ホールで3バーディとして追い上げを開始。その後もバーディを重ね、トップの今野康晴をとらえた。攻め続けた結果、自身初の国内メジャー優勝を果たした
「寝るまでにやることが
どんどん増えて
ちょっと大変です(笑)」
「早咲き」ではなく、「遅咲き」でもなく、「長咲き」のプロゴルファーでありたいと、深堀は願う。
2009年に左足底筋膜炎が悪化し、2011年には手術もした。2012年は1度だけ行使できる「生涯獲得賞金25位以内」の資格で参戦。崖っ縁から賞金ランキング43位でシード権再確保の「返り咲き」に成功した。
昨年はコマツオープンでシニア2勝目を挙げてみせ、シニアツアーでもなお、咲き誇っている。
今になって思うと、「時代」って、ありますよね。僕ら以前はジャンボさんの時代で、「おまえらもプロなら、必死になって俺にかかってこい」。そうおっしゃっていただけて、僕らの時代は一人ずつがその必死さで少しずつ勝てるようになりました。ジャンボさんを超えられはしないけれど、プロとしてやっていけるようになったんです。
同世代の活躍が互いの刺激になって、僕はその中では勝つのにも時間がかかりました。でも思っていたのは、どんな試合でも勝てるのはたった一人だけ。だから勝てるようになるには順番があって、その順番がいつ来るかはわからない。自分にまだ足りないものを積み重ねて、準備をし続ける我慢強さが、プロでは必要なんだと。
僕らの時代からしばらく強いゴルファーが数多くは出なくて、新陳代謝がうまくいかない時代もありました。石川遼の出現は、漫画のヒーローのようで待望の存在でした。そしてまた新たな時代に入ったとき、最初は若い子を相手に必死になっている自分が、大人げないように感じられて、なんか変だなと思えたのも事実です。
だけど、ゴルフは50歳からまたシニアという新しい世界が待ってくれている。体が思うように動かないし、道具の変化もあるし、トイレにこもって戦っていた頃の情熱にも、残念ながら到達できないこともある。準備にしても、歳を取るたびごとに、寝るまでにやることがどんどん増えて、ちょっと大変です(笑)。
だけど、シニアツアーは同窓会のようでもあって、同じ時代を戦ってきた仲間とまた戦えるのが嬉しかったんです。誰もがそれぞれ、ジャンボさんに教わったように、必死にやってきて、ここでまた会えたね、ご苦労さん、と。
僕は若い頃はお酒を誰とも飲まなかったんです。それが今は飲みながら仲間と話す機会を増やしました。そして、やっぱりまた、自分らしく、みんなにまた一歩ずつ追いついて、勝てるようになろうと。早咲きでも、遅咲きでもなく、どれだけ長く咲いていられるか。一昨年に手嶋多一が日本シニアに勝ったから、次は僕の番かな、なんてね(笑)。



● ● ●
都内のオフィス街にある室内ゴルフ練習場に併設されているカフェバーでのインタビューだった。そこで彼は球を打つことなく、予定時間を過ぎても真剣に語ってくれた。テーブルに置かれた、彼が注文したアイスティーに口をつけることも忘れ、グラスの中の氷はすっかり解けてしまった。
なぜか、劇的な場面を迎えることが多い選手がいる。深堀はその最たる例だ。2008年のマイナビチャンピオンシップ、プロ初優勝の石川遼が池からウォーターショットをピン3メートルにつけた最終ホール。2位の深堀もまた、8メートルのバーディパットを沈めてみせた。
「遼が初めて勝つ、時代の変わり目に僕がいられたのは幸せです」
日本の男子ツアー史に残る名場面を、懐かしげに振り返った。
「あのときは勝てませんでしたけど、僕って、臆病なくせに、逆境には強かったりするんですよね」
室内ゴルフ練習場の大きな窓からは、春の強風に揺さぶられる街路樹が見えた。もしもこの先、こんな日に試合があったなら、深堀お得意の、劇的な場面がまた、訪れるのかもしれない。

月刊ゴルフダイジェスト2023年6月号より


 レッスン
レッスン ギア
ギア プロ・トーナメント
プロ・トーナメント コース・プレー
コース・プレー 書籍・コミック
書籍・コミック