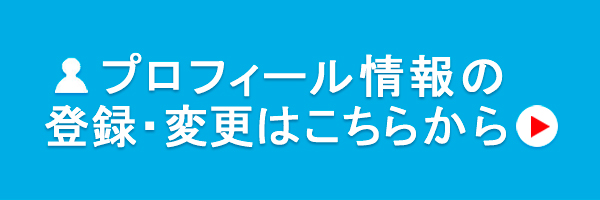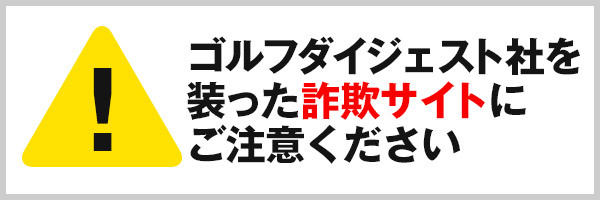小説家、政治家、ヨットマン、ゴルファー。石原慎太郎“流”を貫いた人生
 週刊ゴルフダイジェスト
週刊ゴルフダイジェスト
石原慎太郎は生前、「ぼくは肉体派だから、肉体が消滅すれば何も残らない、虚無だ」と語っていた。その肉体を駆使して、石原はヨットに心血を注ぎ、サッカー、テニス、そしてゴルフにも情熱を傾けた。
写真/長濱治

ゴルフを本格的に始めたのは、23歳で芥川賞を受賞した直後からだという。その頃、文壇ゴルフというものが存在し、当時の“横綱”が丹羽文雄と石川達三だった。石原はイキのいい新人として、文壇ゴルフに迎えられ、丹羽学校へも度々顔を出している。番付では大関格だったという。文壇ゴルフでの一コマを石原が開陳している。
「程ヶ谷でね、キャディが『今、石原さんがトップにいますから、最終ホールだけは自重してスプーンでいきましょう』と言うんだけれど、そんなもんケチケチしなくていいと、ドライバーで打ったら連続OB。吉川英治さんから『君のゴルフは大器の様相があるが脇が甘い』って言われたね」
石原のプレーぶりが彷彿とするエピソードだ。
石原は当時、東急グループ総帥だった五島昇に可愛がられ、弟分的存在。五島の人脈形成倶楽部というべきスリーハンドレッドCを造るために、五島と一緒にヘリコプターに乗り込み、用地探しまでしている。当然石原は若輩ながら最初から会員だ。
石原のご近所さんで、石原がオーナーであるヨットのクルーでもあった今岡又彦はこう話す。「まだぼくが学生の頃からよく誘ってくれましてね。スリーハンドレッド、全部ゴチです。石原さんはドライバーはよく飛ぶし、上手かったですね。感心したのはキャディへのチップのあげ方。現金ではなく、ラウンド数を実際よりハーフかさ上げして1.5Rと書いて渡すんです。これはイキだと思いました。年中誘ってもらいましたが、それも長男伸晃くんが大きくなってからは用済みになりました(笑)」。石原はHC7までいったという。
石原は死すれば虚無と言ったが、石原の思い出が記憶に残る限りは、家族やまわりの人にとっては、決して虚無とは言えまい。

文学(政治家と2足の草鞋)と音楽で日本をリードしてきた同年代の神津善行と。石原の自宅で最後のゴルフ談義(2020年新春号 「チョイス」より抜粋)
ゴルフだけは父親の顔があった

石原慎太郎は「父性」の人だと思う。
石原にとってゴルフの原風景は生まれた小樽にある。石原自身の回顧によれば――。小学生の頃、父親に連れていかれた牧場のようなコースで、そこかしこに牛の糞が落ちていた……。長じて初めてクラブを握ったのは高校生の頃。亡くなった父親のクラブと、ビスケットの箱にしまってあったスモールボールを持ち出して、逗子の海岸で1人打っていたという。
父親は小樽CC(銭函)の会員でクラブチャンピオンを争ったとき、優勝候補だったにもかかわらず、豪打すぎて自滅した話を石原はよくした。そんな父親のゴルフ好きの血を石原は家族に伝えたような気がする。
しかし、石原が教えたわけではないという。典子夫人、そして4人の子どもたち――伸晃、良純、宏高、延啓――は大人になってから思い思いにゴルフを始めている。
ゴルフと家族の関係を石原は次のように述べている。
「家族みんなでゴルフすることは共通の話題があっていい。一緒にプレーすれば普段は見えないところも見えてくる。お互いのスウィングやプレーぶりを見て思ったことを言い合ったり、客観的視点でお互いを見られる。喜怒哀楽、そしてボヤキを共有もできる。親子に欠けがちな感情の共有ができるんだ」(週刊ゴルフダイジェスト2005年7月12日号)
そこにはタカ派としての政治家の姿は微塵もなく、石原家の“父親”が確かにいる。(敬称略)

延啓のショットを見る慎太郎。いちばんの飛ばし屋は良純だったが、飛ばしで息子たちに負けても悔しがらなかった(写真提供/石原家)
文/古川正則(特別編集委員)
週刊ゴルフダイジェスト2022年3月1日号より


 レッスン
レッスン ギア
ギア プロ・トーナメント
プロ・トーナメント コース・プレー
コース・プレー 書籍・コミック
書籍・コミック