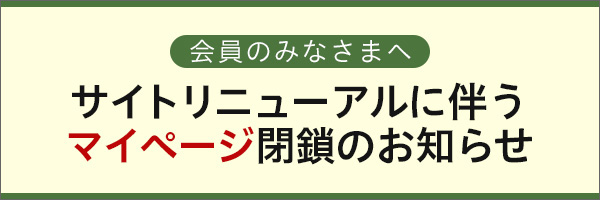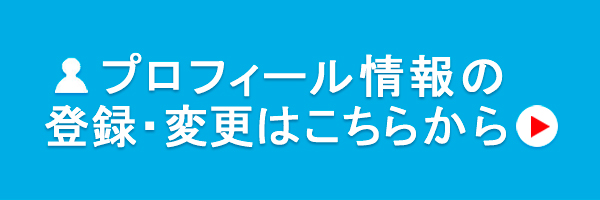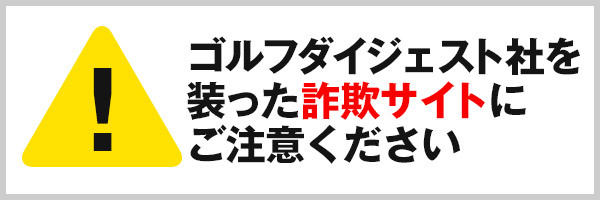【ターニングポイント】羽川豊「家の隅に転がっていた長尺パターに僕は救われました」
 ターニングポイント
ターニングポイント
一流と称される者には、自身のゴルフスタイルを確立するためのきっかけとなった転機がある。例えばそれは、ある1ホールの苦しみかもしれない。例えばそれは、ある1ショットの歓びかもしれない。積み重ねてきた勝利と敗北の記憶を辿りつつ、プロゴルファーが静かに語る、ターニングポイント。羽川豊の場合、それは、長いイップスから抜け出せた道具との出合いでもあった。
TEXT/Yuzuru Hirayama PHOTO/Takanori Miki THANKS/新宿プリンスホテル

1957年生まれ、栃木県出身。80年プロ入り。レギュラーツアー5勝、シニアツアー3勝。81年「日本オープン」でプロ初優勝を飾り、「日本シリーズ」でも青木功をプレーオフで下して2勝目を挙げた。82年には「マスターズ」に出場し、15位でフィニッシュ。“世界のレフティ”と評された。IPOC所属
容易にできていたことが、ある出来事を境に突如できなくなる。そんな「イップス」という病に、いつ誰が蝕むしばまれるかわからない。それはたとえ、将来を嘱望されたプロゴルファーだとしても。
1980年に当時のプロテスト新記録となる8アンダーで合格した羽川豊は、翌81年には日本オープン、日本シリーズとメジャーを制した。その国内での活躍からマスターズに招待されたのは、初めてクラブを握ってから8年目、24歳のときのことだった。オーガスタでも決勝ラウンドに進出したばかりか、15位と健闘し、「現役最高のレフティ」と現地で称賛された。
けれども、その直後から、無明の闇へと迷い込む。ドライバーが曲がりだし、恐怖心から振り上げたクラブを振り下ろすことができなくなった。4年間予選落ちを繰り返す苦悩の日々、思い余って駆け込んだのは、尾崎将司の軍門だった。
僕のドライバーが2番アイアンの飛距離。
その差に愕然としました
マスターズの結果は15位だったんですけど、このままではダメだなと。僕のドライバーは、海外選手の2番アイアンの飛距離。その差に愕然としました。270ヤードは飛ばしていたんですけど、海外で戦うなら、そんな飛距離ではどうにもならないと、当時の僕には思えたんです。
大手の下請け工場を営んでいた実家が新たに始めたゴルフ練習場で、16歳からとにかく球数を打つことで技術を身につけました。理論武装をしていないし、肉体的な土台もできていない。それなのに無理に飛ばそうとして、スウィングを崩してしまったんでしょうね。
打ち急いだり、力んだり、球筋もバラバラで右に左に曲がる。練習をして上手くなってきたから、必死に球を打つんですけど、打てば打つほど深みにはまって身動きがとれなくなる。トップまではクラブを振り上げられるんですけど、ダウンスウィングで手が異常な反応をしてしまうんです。なぜなら、きっとインパクトでは、フェースが開いたりかぶったりするだろうなと予測できてしまうから。
ドライバーで恐怖心を抱えてしまってからは、予選落ちばかりでシード権を喪失しました。人前でショットを見せるのがプロの仕事なのに、見られていると困るようでは、ゴルフを諦めて仕事を変えるしかないですよね。4年間苦しみ抜いた末に、ジャンボさん(尾崎将司)に相談に乗ってもらったんです。するとこう言ってくれました。
「4年も苦しんできたなら、4年かけてもとに戻したらいいじゃないか。オフに体作りに来い」。

1980年のプロテストをトップ合格した翌年の81年、日本オープンと日本シリーズで優勝。“飛ぶ鳥を落とす勢い”で日本を代表するトップ選手へと上りつめた。その活躍でマスターズの切符をつかんだ
シード選手が10名くらいいるジャンボ軍団の合宿だと、腹筋も背筋も、自分の肉体が彼らに劣っていることがよくわかりました。ジャンボさんはよく言うんです。「心技体ではなく、体技心だぞ」と。
3年が経って徐々に体ができてくると、ある日の練習中、上下左右に軸がぶれていた自分に気付いたんです。つまりは、それに気付ける肉体的な土台が初めてできたということでしょうね。
コースでは最初は怖々と、トップ気味に低い球を打っていました。やがて弾道を高くしても狙いどおりの球筋が出だすと、いつしか恐怖心も消えていました。海外での合宿で、池が張り出した狭いフェアウェイをドライバーでとらえたとき、「おまえ、よくこんな狭いところを狙えるな」とジャンボさんが褒めてくれました。闇夜に光が差したような気分でしたね。
ときに病は容赦なく、一度は克服した者に、再び襲いかかってくることがある。あたかもそれは、何かを試しているかのように。尾崎将司の言葉どおり、4年苦しんだドライバーイップスを、4年かけて克服した。90年にシード権を奪還し、翌91年にはインペリアルで8年ぶりに優勝。しかもその翌週の静岡オープンで、2週連続優勝まで成し遂げた。その後もたびたび上位に進出し、完全復活かと思われたが……。
ショットが良くなったのも束の間
今度はパットが打てなくなりました
ジャンボ軍団で体を鍛えて、ショットが良くなったのも束の間、今度はパットが打てなくなりました。コースのグリーンに立つと、利き手の左手に電気が走るようになったんです。そのせいで変な動きをしてしまい、1メートル以内なのに、押し出したり、引っかけたりの繰り返し。50センチさえ、ポロッ、ポロッと外して、9ホールで3、4回も3パットしてしまうんですから。
握り方をどんなに変えてもダメ。100本以上パターを替えても、メンタルコーチを付けても、全部ダメ(笑)。2打目でピタッとピンそばに寄せても、絶対に入らないだろうなと。案の定カップを行ったり来たりしていると、俺はホールアウトできないんじゃないかという不安に襲われたことさえありました。
そして、2000年の日本プロでも散々で(初日80、2日目79で128位タイ、予選落ち)、その年できっぱりやめようと思いました。ドライバーのときはまだ頑張ればどうにかなるかなと思えましたけど、パットのイップスは万策尽きました。



人生には「出合い」がある。それは人との「出会い」ばかりではない。
パットのイップスによって引退を決意し、テレビ解説者に転身した。全米オープン、全英オープンなど、数々のメジャーを10年以上にわたってリポート。プレーするのではなく、試合をロープの外側から見つめるのが仕事になった。若かりし頃のタイガー・ウッズをはじめ、スーパースターのプレーを間近に見ると、あらためてゴルフの楽しさを実感した。
そして、シニア入り目前の49歳になった2007年、家の隅に転がっていた、それまで見向きもしなかった一つの道具が、彼を再び、ロープの内側へと戻してくれた。
もう選手としては、未練はありませんでした。どうせパットを外して負けるだけだとわかっているんだから、これほどつまらないことはない。とはいえ、クラブを投げつけるようにして終えたのではなく、クラブをそっと置くような引退でしたね。
試合を外から見るようになると、なんの苦しみもなくプレーしている若手を見るのが、楽しくてね。全米、全英での海外のトッププロは、僕の想像から絶対に逃げないんです。この深いポットバンカーから出して近いピンに寄せるには、わずか数cmしかない縁にぶつけてショックをやわらげて転がすしかないな、と想像すると、そのとおりにやってのけてしまうんですから。
“魔法の杖”を得て
もう一度競技の世界へ戻った
テレビの仕事を続けていた2007年のある日、家の隅に転がっていた長尺パターに、なにげなく目がとまったんです。誰が送ってきてくれたものかもわかりません。それまでの僕には、長尺なんか使ってゴルフができるかという固定観念があったから、見向きもしませんでした。握ってみると、ネックがグラグラ動いてね(笑)。
それを調整してコースへ出て、1番グリーンで2メートルのパットをドキドキしながら打ってみました。入りはしなかったんですけど、ヘッドがスッと動いてくれたんです。あれっ? 俺が狙ったラインに転がるじゃないかと。
グリップは、握る位置によってはまだ左手に電気が走るような感じがしたんです。でもシャフトの下側を、手のひらを目標方向に向けて握れば大丈夫なことを発見しました。もしかしたら、この「魔法の杖」となら、試合にも出られるんじゃないか、そう思えてきたんです。

パットのイップスで一度は引退を決意していた羽川だったが、長尺パターのおかげで競技へ戻ることができた。「狙ったラインに転がせるこの“魔法の杖”となら、試合にも出られる」と思ったという
「魔法の杖」である長尺パターとともに、50歳になった2008年、シニアツアーに参戦した。
復帰後4年目の2011年、PGAフィランスロピーシニア。首位と4打差の8位タイで迎えた最終日、まさに魔法がかったパッティングで猛追を見せる。11番で13メートル、12番で5メートル、16番で10メートルをカップイン。短いパットもことごとく決めてみせ、10番からの3連続を含む7バーディ、1ボギーのベストスコア66を叩き出して通算10アンダー。首位に並んでプレーオフの末、シニアでは初めての、ツアー競技では実に20年ぶりとなる栄冠を手にした。
2度のイップスによる苦悩の果てに、一度はクラブを置きながらのカムバック。リポーターとして長年選手に向けてきたマイクを、この日は自身が向けられたその勝利者インタビューで、しみじみと彼は言った。「優勝って、こんなに嬉しいものなんですね」
2011年のPGAフィランスロピーシニアの頃には、長尺のおかげで戦えることはわかっていました。グリップエンドを固定して支点を作り、ヘッドを振り子のようにゆっくり動かす。小さな筋肉が微妙に動いてしまわないから、長尺って、いいなと。パットさえ入れば勢いに乗れるし、そんなスコア(最終日の66)もまだまだ出せるということが、この歳になって自分で再認識できました。
イップスに2度も苦しんだ僕が言えるのは、もうダメかなと思ったところから、固定観念を捨てて、新しいものを探すことも大切だということです。ドライバーのときの体づくり、パットのときの長尺と、模索し続ければ、出口が見つかることもあるわけだから。
昔には戻らないほうがいいと思うんです。
時間が解決したものにこそ価値があります
ダメになったとき、昔に戻りたいと言う人がいるじゃないですか。だけど僕は、昔には戻らないほうがいいと思うんです。人間って、変わってゆくものだし、戻ろうとするよりも、新しい自分を作っていくほうがいい。時間が解決したものにこそ価値がありますから。シニアになっても体が動く自分を作りたい。そのために毎朝5時に起きて走って下半身を強化したこともありました。プロって、勝てるかもしれないという、夢を追えるから、続けていけるんですよね。それがある限りは、たとえ悔しい負けがどれだけ積み重なろうとも、これからもやっていこう、そう思っています。
● ● ●
シニアツアーに参戦しつつ、2016年からは母校・専修大学ゴルフ部の監督に就任し、後輩の指導にあたってもいる。
63歳になる彼が、10代、20代の若者たちに何を伝えようとしているのだろうか。「プロになれるのは、ほんの一握り。思いどおりにいかないのが社会だから、ナイスショットばかりを求めるのではなく、忍耐強さが、大切なんだよ、と」
今年の大学の合宿では、朝寝坊した3年生に雷を落としたという。祖父のような年齢の強面の監督は、学生よりも早起きで、そして、ゴルフにまだまだ真剣だ。

月刊ゴルフダイジェスト2021年9月号より


 レッスン
レッスン ギア
ギア プロ・トーナメント
プロ・トーナメント コース・プレー
コース・プレー 雑誌
雑誌