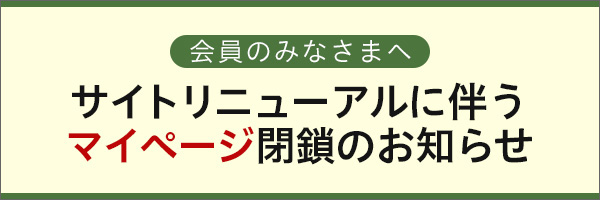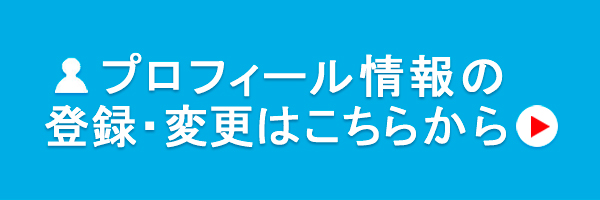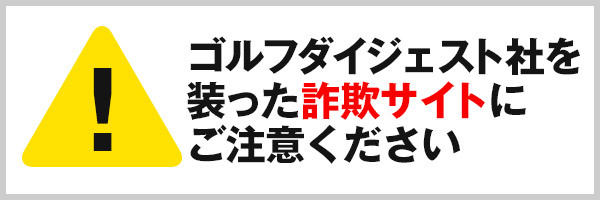【ターニングポイント】田中秀道「僕の人生はすべてが“紙一重”」
 ターニングポイント
ターニングポイント
プロゴルファーになれたのもプロゴルファーでなくなるのもひとりひとり、理由がある。貧しい環境で祖母に育てられ小柄ながら反骨心で飛距離を伸ばした。日本ツアー10勝、アメリカへ5年間参戦。けれども、長年の無理が体や心を虐げた。人生の「紙一重」が幾重も存在した田中秀道の、ターニングポイント──。
TEXT/Yuzuru Hirayama PHOTO/Takanori Miki

「『いいんじゃないですか』で
父親のボルテージが
上がったのが見て取れました」
過酷な幼少期がその後の糧となることはままあろう。
母を知らず、父はたびたび家を空け、祖母に育てられ、腹も心も満たされない日々。夢も希望もなく、いつ道を外れてもおかしくはなかった。そんな少年を救ったのは、ほんのささやかな、空き地での球打ち遊びだった。
僕の一番古い記憶は、幼稚園に行くのに祖母の千代子が連れて行ってくれたことが、少し恥ずかしかった、という思い出ですかね。僕が生まれてすぐに父と母が離婚し、もしかしたらまだ生きているのかもしれないですけど、母には会ったことがないんです。
建築業だった父の等は、自分で事業を始めてもなかなかうまくいかず、家にいないことも多かったです。祖母に育ててもらったんですけど、賃貸アパート住まいで風呂がない家に住んだこともありました。食事も納豆とご飯くらいで、肉さえ食べた記憶がない。外食したこともなければ、一家で食卓を囲んだこともなかったです。
中学生までそんな生活でしたから、もうどうなってもいいやと、道を外れてしまいそうになったこともありました。僕の人生はすべてが紙一重で、ただ、祖母の姿を見ていると、もうやっていられないと生活を投げ出してしまいたくなるのは、祖母のほうじゃないかと。祖母のためにも、非行に走っている場合じゃない、僕がこの家の流れを変えるんだと思い直しました。
ゴルフなんて100パーセントできない環境でしたけど、ある日、小学6年生のときの友だちの一人が、お父さんのだいぶ使い古した7番アイアンを持ってきたんです。それでプラスチックの穴開きボールを打って遊びました。正方形の空き地の角に4つ穴を開けて、そこに入れるだけの遊びです。そこへ「おまえら、何やっとんじゃ」と父が来て、ゴルフをして遊んでいると答えたら、近所の打ちっ放しへ連れて行ってくれたんです。
たまたまそこにいたレッスンプロが、僕が打つのを見て、「この子、いいんじゃないですか」と言っちゃった(笑)。父のボルテージが上がったのが見て取れました。そこからは中学3年生まで、毎日練習です。おカネがないので練習場の裏手にあった無料のバンカーで球を打つんです。友だちと遊んだこともなく、父に怒鳴られながら泣かない日がなかったくらい。深夜2時から公園の砂場で練習して、そのまま学校へ行くようなこともしていました。どうせ、その頃の僕にやれることは、ゴルフしかなかったですから。
「祖母には自分しかいない。
絶対に成功しなきゃという
反骨精神だけでやってきた」
身長は166センチ、体重は60キロ足らず。師匠・石井哲雄から弟子入りを断られた小柄な青年は、しかしプロとして稼ぐという夢を諦めてしまうわけにはいかなかった。
2度目の直談判で弟子入りし、4度目のプロテストで合格。そこからは死に物狂いの執念で、1998年の日本オープンをはじめ、ツアー10勝するまでに成功する。
試合に出始めた高校時代の成績は、まったく大したことがなかったんです。それでも、高校を卒業したらゴルフ場の研修生になって、最短距離でプロになると考えていました。大学進学なんて経済的にできません。高校のゴルフ部監督に勧められて、石井哲雄プロのいる兵庫県のゴールデンバレーGCへ面接に向かいました。
ところが石井先生から、「その体格ではプロの世界は厳しいから帰りなさい」と。2時間ぐらい「いや、絶対にやれます!」と粘ったのですが、渋々広島へ戻りました。それでも納得がいかず、もう一回石井先生に会いにいくと、本部長が出てきて「無理やから帰れ!」と。僕は1秒も目をそらさず、「絶対にプロになります!」と言い続けました。まるで本部長とメンチ切り合いみたいな(笑)。
どうにか研修生になって、住み込みで月給は5万円。そのうちの2万円を祖母に仕送りしました。プロテストには3回落ちて、4回目で通りました。祖母には自分しかいない。祖母を楽にさせたい。プロになっても僕の原動力は、絶対に成功しなきゃという反骨精神だけでした。
こだわっていたのは飛距離です。高校時代から「ちっちゃいけど飛ばすヤツ」と言われると嬉しくて。恵まれている大学生なら、クラブが飛ばなければ買い替えてもらえます。それにいくらでも球を打てます。でも恵まれていない僕は、クラブの特性を考え、球を打たずに素振りでどう動けば飛ばせるかということを考えていました。スローモーションで、体の動きを脳から伝達して、1分以上もかけてひと振りするという練習もよくやりました。恵まれているやつにそういう執念があったら、もう勝てません。だからねたみやそねみから生まれた感情でしょうけど、恵まれているやつは、その執念に気付くなよ! と思ってましたね。
1995年のフィリップモリスチャンピオンシップで、ツアー初優勝。ウィニングボールを祖母にあげようと、ギャラリーに投げるボールをもうひとつ、ポケットに忍ばせていたんです。そうしたら最終ホールでカップインした途端、涙が止まらなくて。結局ボールは投げられず、ウィニングボールが2つになってしまいました。


最終18番、大洗GCの松林から50センチ四方を抜いたサードショットでグリーンをとらえ、1打差をつけてビッグタイトルを奪取した
活躍する日本での安泰を捨て、2001年、米ツアーのQスクール最終予選を通過。だがそれは、文字通り危険な挑戦となってしまい、結果として肉体に負った代償は、あまりにも大きなものとなった。
「120パーセントのフルスウィング」を続けた無理がたたり、首の神経麻痺、腰骨の圧迫骨折、肩関節唇の裂傷。脳からの四肢への司令も以前のように伝達できなくなり、傷心のままにクラブを置くことになった。
世界最高峰の環境でゴルフがしたいという思いもありました。だけど一方では、金銭的にも体格的にも恵まれていない子どもたちに夢を与えられたらなと、そんなことも思っていたんです。調子に乗っていたんでしょうね(笑)。
2002年、米ツアーでの最初のシーズンが始まってすぐに、えらいところへ来たなと。飛距離に関しては日本ではそれなりのところにいたんですけど、アメリカでは50ヤードも置いていかれました。
忘れられない衝撃は、海辺のハーバータウンGLでのこと。物すごい強風の中で必死に回って、今日は最高のプレーができて1アンダーだった、やったぞと。ところがスコアボードを見たら、予選カットぎりぎりの順位なんです。ホールアウト後にテレビでは、デービス・ラブⅢがトロピカルドリンクを飲みながらインタビューを受けていて、「リゾート気分でリラックスしてプレーしたのがよかった」と、9アンダーでトップでした。8打差が、40打差くらいに感じられたほどにショックでした。
結局、5年間アメリカで戦いましたけど、ずっと空回りで終わってしまいました。日本時代からこの小さな体格で120パーセントで振っていくスタイルでしたから、人一倍体をメンテナンスしなければならなかったのに、アメリカではなかなかそれもできなくて。
帰国後は、アメリカで体の悲鳴に耳を傾けなかった代償で、首も腰も肩も壊して、脳からの司令もうまく体に伝わらない状況でした。僕はぎりぎりまでパワーを溜め込んで、フォロースルーのキレで飛ばすというタイプでした。それなのに肝心のキレがない。ドライバーのヘッドが大きくなってきていた頃だったので球がつかまらない。球が操れなくなったところからやがて、メンタルまでやられてしまいました。
ダンロップフェニックスの1番ホールで、ギャラリースタンドに球が当たりかけたことがありました。ウッドで打っているのに、シャンクみたいな出球で。そこからは、もう完全にイップスに陥って、ティーショットのことを考えるだけで過呼吸になるほどでした。いまだに、体も、イップスも、治ってはいませんね。
「うっすらと復帰したい
気持ちはある。だけど今は
自分と向き合う日々」
まだ、52歳。
しかし、レギュラーツアーや、シニアツアーはおろか、プライベートゴルフさえも、満足に回れずにいるという。
一度は頂点を極めたプロゴルファーが、隣の、その隣のホールまで、真横に飛ぶ球のもとへ歩く。無惨な現実に打ちひしがれながらも、彼はまだ、少しの希望を捨てずにいる。
2年前に医師からは、「こんな状態ならゴルフなんて、もうできないですよ」と告げられました。腰骨のレントゲンで、ある骨が潰れていて黒くなっていました。それでも、シニアツアーに参戦できる年齢になったので、一度だけ出てみたら、90を切るのがやっとでした。なんせ、2打目が全部、隣の、ときには、その隣のホールから打たなければならないんですから。
左で打ってみようかと、左利き用のフルセットを買ったのですが、ゴルフって、そんなに甘いものでもなく。一緒に戦ってきた仲間たちと、半分笑いながら、半分真剣に、もう一度同じコースに立てたらと、夢を見ることもあります。ただ、本番はもちろん、プロアマにこそ、僕は出られません。カッコつけられないからではなく、変な所へ飛んだらどうしようと、迷惑をかけてしまうのが怖いから。もう、プライドなんかないんです。全盛期の自分を見せようという気持ちもなく、お願いだから、確認できる所に飛んでくれさえしたらと。
今でもひょっとしたら、僕の姿を見たいという人も少なからずいてくれるのかもしれません。僕自身も、うっすらと復帰したいという思いはあるんです。だけど今は、自分の現実と向き合う日々ですね。ツアープロだったのは過去のことで、それを受け入れてもいます。そのうち、「笑えないミスがあったけど、78で回れたよ」ってツアープロを彷彿させるような会話を、穏やかな気持ちで語れるような場所へ、いつかはたどり着きたいですね。



● ● ●
インタビューは、「東京マラソン」の当日だった。
「天気が良くて、ランナーたち、よかったですね」
東京タワーの麓を駆け抜けるランナーを見送りながら、田中秀道は微笑みながら言った。
ランナーにとっては走ることが、ゴルファーにとっては打つことが、この晴天ならば当然の幸甚だろう。
しかし、プロゴルファーの彼なのに、ゴルフウェアではなく、黒いジャケットを羽織ったその姿が、すっかり見慣れてきた。
「ゴルフをしたくとも、知らない人とは、まだ回れません。だって、元ツアープロがOB連発で、暫定球7球目とかになると、もう誰も笑えないでしょ」
芝公園付近の、38キロを過ぎた地点。東京駅前のゴールへと続く、最も過酷な最後のUターンが、そこにはある。
彼はもう何も話さず、しばらくそこで、目の前を行き過ぎるランナーを、幾人も、幾人も、見送っていた。

月刊ゴルフダイジェスト2024年6月号より


 レッスン
レッスン ギア
ギア プロ・トーナメント
プロ・トーナメント コース・プレー
コース・プレー 雑誌
雑誌