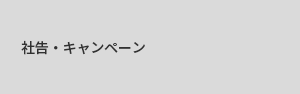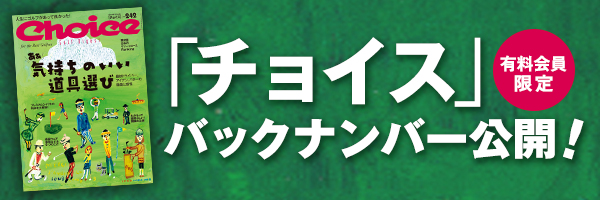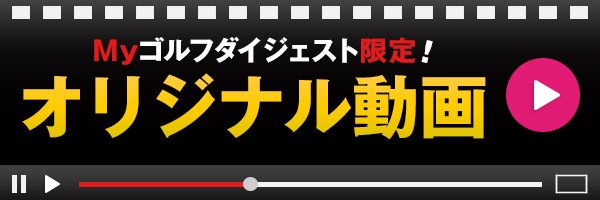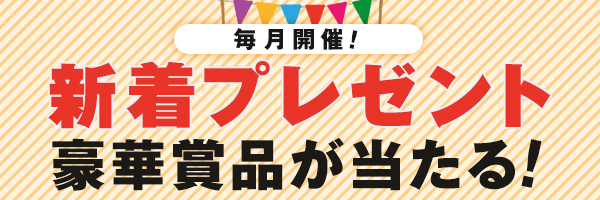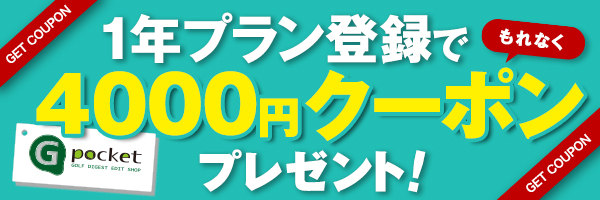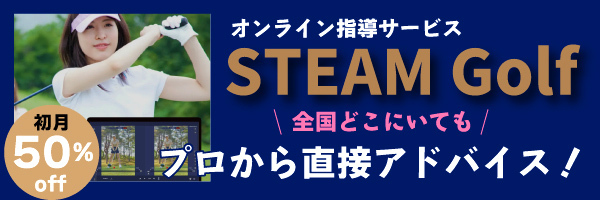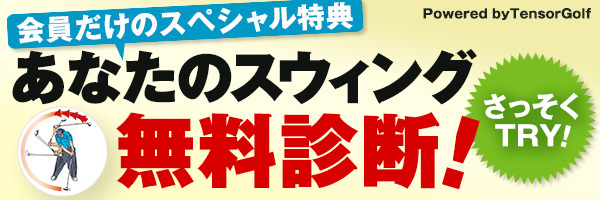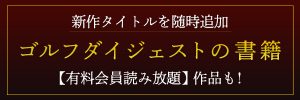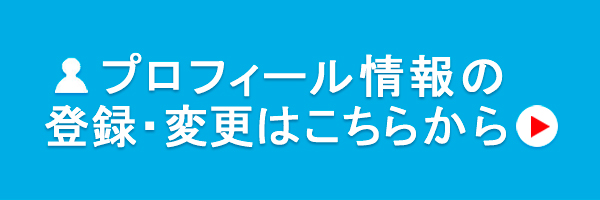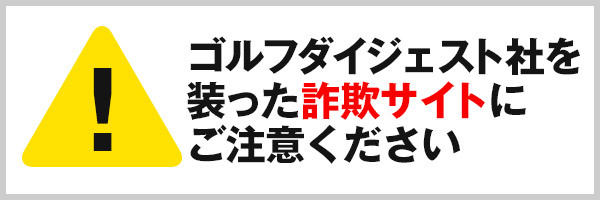【目澤秀憲の目からウロコ】為末大編②「“運動神経”の正体とは?」
 目からウロコ
目からウロコ
いくら練習してもうまくいかない人と、ほんの少し練習しただけでうまくできる人がいる。両者は何が違うのか。俗に言う「運動神経がいい人」は、結局どういう人のことを指すのか?
ILLUST/Masahiro Takase TEXT/Daisei Sugawara PHOTO/Hiroaki Arihara

為末大 世界陸上の男子400Mハードル種目において、2大会(01年、05年)で銅メダルを獲得。同種目でオリンピックにも3大会連続(2000年、04年、08年)で出場。現在は指導者としても活動
>>前回のお話はこちら
- 目澤秀憲コーチが、異業種からゴルフのヒントを得る連載「目澤秀憲の目からウロコ」。今回話を聞きに行ったのは、400mハードルで活躍した為末大さん。陸上競技のトラック種目は己の身体のみが武器というスポーツの中でも最も根源的でその分「難しい」スポーツ。一流のトラックアスリートはどんなことを考えているのか。 TEXT/Daisei Sugawara PHOTO/Hiroaki Arihara ……
動きの中で自分の体を
どのくらい把握できるか
―― 前回、人間の身体制御はほぼ「無意識」で、だからこそ動きを変えるのは難しいという話がありました。
目澤 コーチとしては、どういう言葉で選手にアプローチすべきか、常に考えていかなきゃいけないと改めて感じました。ひとつの言い方でダメなら、別の言い方、それがダメならまた別の言い方、というふうに選手に届くまでやる必要があると。
為末 コーチが伝えたい動きの全体像を選手が把握するまでは、「何を言っているかわからない」という状態になることも多いですね。「走る」という動作の中に「腕を振る」という要素と「足を出す」という要素があって、腕に関して言うコーチと、足に関して言うコーチがいた場合に、これは単に「視点」が違うだけで、結局は同じことを言っている可能性が高いわけですね。全体像が見えている選手であれば、自分の中で2つの情報を統合できるんですが、そうでない場合はただ混乱するという(笑)。
目澤 ゴルフの場合、スウィングだけじゃなくて、身体機能やメンタル、クラブやボール、それにコースや自然環境を全部ひっくるめた複合問題になってしまうので、その部分がかなり大変です。いかに必要な情報だけを整理して伝えられるかというところが。
為末 そうやって苦労して伝えたとしても、実際にパフォーマンスにつながるかどうかは、選手の体の自己認識によるところも大きいです。「重心をぶらさないで」と言っても、走っているときに重心がどこにあるか、本人がわかっていないことも多い。
目澤 それこそ、プロは無意識にできている部分がほとんどなので、うまくいかなくなったときに自分では原因にたどり着かないケースがあります。自分がどうやってスウィングしているのか、言葉で説明できる人のほうが少ない気がします。
為末 体の自己認識がどういうものかを人に伝えるのは難しくて、ひとつの例で言うと、ほうきを手のひらにのせてバランスを取る遊びがありますが、あれなんかは割と伝わるんじゃないかと思います。仮に、ほうきの傾きが2~3度くらいだったらバランス回復可能で、4度になったらアウトだとすると、長く続けたいならほうきが傾いていることにできるだけ早く気付けるほうがいい。2度未満で気付けばまずまずなのかもしれませんが、それを0.5度で気付けるかどうかが大事なんですね。
目澤 よく「運動神経がいい」っていいますが、それって自己認識とか、動きの変化の察知能力のことなのかもしれませんね。
為末 それは間違いないです。もうひとつ、運動神経の「正体」だと言われているのが、身体操作の「巧みさ」ですね。これは、ロシアのベルンシュタインという運動生理学者が「デクステリティ」(※)という本の中で言っていることなんですけど、人間の筋肉とか腱ってゴムみたいにある程度の弾性があるじゃないですか。しかも筋肉って、つながっている骨を「引く」ことはできても「押す」ことはできないんですね。棒の先に鉛筆か何かを括り付けて、それをお腹のところに固定するとしますよね。で、それを棒につながった2本のゴムひもを両手で操作して絵を描くとしたら、ものすごく難しいじゃないですか(笑)。そんな難しいことを人間はやっているんだと。ひもの操作が上手い、つまり「巧みな」人ほど運動能力が高いというわけですね。
※「デクステリティ 巧みさとその発達」 ニコライ A・ベルンシュタイン著 工藤和俊訳 佐々木正人監訳 金子書房刊

先端の重りと腹部をつなぐ棒が「骨」、左右の手で操作するゴムひもが「筋肉」を表している。筋肉は骨を「引く」ことしかできず、しかも伸び縮みしてしまう。先端操作がいかに難しいかは想像に難くない
自己認識で運動結果に差が出る
手のひらにほうき(棒)をのせてバランスを取る遊びでは、ほうきの重心の傾きをいち早く察知できる人ほど長く続けられる。仮に察知能力が同じならば、自分自身の動きを正確に認識できる(=体の自己認識能力が高い)人が有利。さらに、身体操作の「巧みさ」に長けている人であれば、さらに長時間バランスを保てる

月刊ゴルフダイジェスト2025年5月号より


 レッスン
レッスン ギア
ギア プロ・トーナメント
プロ・トーナメント コース・プレー
コース・プレー 書籍・コミック
書籍・コミック