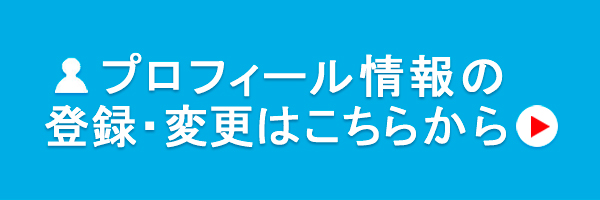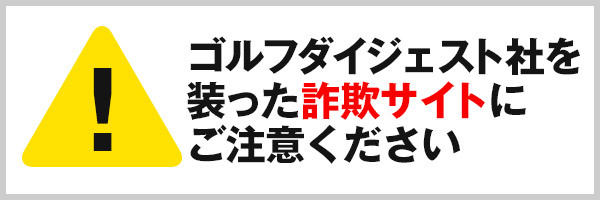【ターニングポイント】水巻善典「僕はゴルフが好きじゃなかったプロゴルファー」
 ターニングポイント
ターニングポイント
プロゴルファーといえど、ゴルフが好きではない者もいる。スコアにも、順位にも、賞金の多寡にもさほど興味はなく「面白いと感じたことがあまりない」。米ツアーでも活躍し、シニア入りして10年以上が経過。63歳が語るゴルフ観と幸福感の「ターニングポイント」──。
TEXT/Yuzuru Hirayama PHOTO/Hiroyuki Tanaka THANKS/鳴尾ゴルフ倶楽部

1958年、東京都出身。84年にプロ入りし、89年の関東オープンでツアー初優勝。93年、米ツアーのクオリファイングトーナメント(QT)を受験して合格。94年より一時米ツアーに参戦し、日米両ツアーのシード権保持者として活躍した。ツアー7勝、シニアツアー3勝
兵庫の名門、鳴尾ゴルフ倶楽部。
厳かなほどに古めかしいクラブハウス内のバーに水巻善典は現れた。革張りのソファに腰を下ろすなり、「思い出を語ることはあまり好きではないんですよ」と彼は言った。それでも、グリーン改修工事に伴う休場による、誰もいない静寂もあってか、時間をかけて、記憶をたどってくれた。
勝ちにいって勝てるのは超一流のプロだけ。
“勝つ”とは“勝っちゃう”ことだと思っていました
東京の下町、足立区梅田で印刷機械の下請工場を経営していた父(外吉)に、小学生の頃に練習場へ連れて行かれたのが、ゴルフとの出合いです。父はゴルフが好きでしたよ。僕は好きじゃないけれど(笑)。僕がやっていた野球もバスケットボールもチームスポーツで、みんなでワイワイ楽しかった。ゴルフは個人の成績が、いいか、悪いか、そんなのはつまらなくてね。
ところが法政大学4年生のときに日本学生選手権で2位になってしまって、プロになるということを少し意識しました。長男だから父の工場を継がなければならないのに、レールの上に乗る人生よりはちょっと外れたいなって。プロを目指してしまったんです(笑)。
プロになってみると、ゴルフがさらに楽しくない。だってアマチュアみたいにどれだけミスをしても、気持ちのいいショットが一つ出ればビールが旨い、というわけにはいかないでしょう。プロは逆で、いくらいいショットばかりでもミスが一つ出れば練習しなければならない。しかも飛距離を出そうと、(尾崎)直道さんを真似て頭を振って飛ばそうと練習していたら腰を痛めてしまってね。
僕にとってゴルフは、トライをして楽しめるゲームではなく、スコアのためにそのトライしたい感情を抑えつつ回るしかない「仕事」。仕事だから、そのときどきで一生懸命いいスコアを出さなきゃと、それだけ。練習も仕事のうちだからする。ただ、自分で決めていたのは、最後の一人になるまで練習場にいようと。青木(功)さんやジャンボ(尾崎将司)さんのような凄い人たちほど上手くないわけだから、やるしかないよなと。
転機は1989年の関東オープンでのツアー初優勝。青木さんと優勝争いをしているさなかには、僕が青木さんを凄い人だと仰ぎ見ていました。だから青木さんが最終日の18番でグリーンを外しても、この凄い人ならチップインしてくる、そう思い込んでいたんです。だけどそれを外されたこともあって、1打差で勝てました。表彰式でその青木さんと目が合ったんです。その瞬間、ああ、青木さんも僕らと同じ人間だったんだと。そのことに気付けて、そこからは自分のペースでプレーできるようになったんですよね。



フェアウェイを外さないステディなゴルフが身上
初優勝をした89年のドライバーショットを見て、当時から「フェアウェイを外す心配を、あまりしたことがない」と水巻。今も昔も安定感抜群のスウィングは変わっていない
水巻といえば有名な逸話がある。初優勝の関東オープン3日目、17番のグリーン上でバーディパットを狙う彼の球を、テレビカメラがアップでとらえた。球には彼がマジックで線を書いており、テークバックの際、その線がほんの微かに動いたかのようにテレビに映し出された。ホールアウト後、それを指摘された彼は、潔く2罰打のペナルティを受けた。そして、その2罰打をものともせず、初優勝。けれども、「それはドラマチックでも何でもない」と彼は語る。
僕は、「勝ちにいこう」なんて思って試合をしたことはありません。初優勝の関東オープンで、トップに立っていてもそう。いくら僕が「勝ちにいこう」としても、勝てるかどうかなんてわからないから。だから2罰打を受けても特別ショックということもなかったんです。逆に、初優勝したからといって特別嬉しいということもなかったけど(笑)。当然涙も出ないし、周囲で喜んでくれている人の姿を見て、ああ、よかったなって、その程度。
「勝ちにいこう」として勝てるのは、超一流のプロだけ。全員のスコアを上回って、力の差で勝ちにいって勝つというのができるのは、日本ならジャンボさん、アメリカならタイガー・ウッズくらい。それ以外のほとんどは、誰かが崩れたり、調子が悪かったり、他の要因がありますよね。
僕にとって「勝つ」とは、「勝っちゃう」ことだと思っていました。だから初優勝も、ドラマを作りたい人が、「2罰打を乗り越えて青木さんに勝った」とか言ってくれますけど、そんな劇的なものではないんです。あのときは青木さんだけじゃなく、横島由一さんも、横山明仁君も、ベストアマの深堀圭一郎君もいて、青木さんとだけ戦っていたわけでもないですし。その彼らに何かミスや不運があって、僕が「勝っちゃった」だけ。
だから僕がやってきたのは、「勝ちにいこう」ではなく、自分に足りないことは何かを考え、それを少しずつ減らしていく「仕事」。それは、プロゴルファーでなくとも、他の「仕事」でも、同じでしょ。



アメリカのギャラリーはプレーを見てくれる。
でも、それ以外はあまり幸せではなかったかな
一流と、超一流。
それを分かつ「一線」がある。93年のJCBクラシック仙台でも優勝し、米ツアーのクオリファイングトーナメント(QT)を受験して合格。翌94年の同ツアー、バイロン・ネルソンクラシックではプレーオフの末、2位タイにもなった。日米のツアーで一流の仲間入りをするも、ある超一流との出会いに、「一線」を痛感させられる。
僕はアメリカを目標にゴリゴリやってきたわけではないんです。ただ、91年のザ・インターナショナルに推薦で出してもらえたとき、アメリカは日本とずいぶん違うんだなと思ってね。日本はジャンボさんを見に来る観客が多いですよね。だけどアメリカのギャラリーは、プレーを見てくれる。それが、なんか楽しいかな、と。でも、それ以外は、アメリカではあまり幸せではなかったかな。
なぜアメリカへ渡ったのかと聞かれたら、息子の将来のためという理由が一番で、前の嫁がアメリカ好きだったのが二番で、僕のゴルフは最後だった(笑)。アメリカへ行ってみると、やっぱり面白くない。フロリダ州のオーランドにデカい家を買って、庭にプール、裏には湖、ボートも買ってと、そんな暮らしをしましたが、なぜか幸福感がなかったんです。
94年のバイロン・ネルソン、最終グリーンでワンピンの距離のパッティングを沈められずにプレーオフになって、最終的には2位タイに。あれが入っていたら、翌年のマスターズにも出られたでしょうし、また違う人生もあったのかもしれません。だけど、入らなくてもよかったかな。日本へ帰ってきた、今の人生のほうがいいから。
僕は嫁と息子にアメリカでの財産をすべて残して、独りになって帰国しました。アメリカ時代の僕の財産といえるのは、近所にタイガーが引っ越してきたときの思い出くらいかな。
彼の練習を見ていて、3番アイアンでも5番アイアンでも、同じ高さ、同じ球筋で打ってみせるんです。あまりに真っすぐだから、「20ヤード曲げてみてよ」とふざけて言うと、どのクラブでも20ヤードだけ曲げて飛ばせるんです。あるときは一緒にラウンドを終えたあとの練習場で、地面の球をサンドウェッジのフェースで拾うと、そのまま何度かリフティングをして空中に浮かせまま、それを打って見せたんです。それをどのクラブでも繰り返して、最後はドライバーのフェースに球を弾ませると、それを空中で打って「ヨシ、ハッピー?」って笑うんですよ(笑)。こんな超一流に、僕はどんなに努力してもなれっこないと思いました。
ゴルフはアマチュアのためもの。
皆が喜ぶために自分は何ができるのか
シニアツアーと、レギュラーツアーとの違い。
それは選手の年齢ばかりではないことを、水巻善典のプレーが教えてくれる。彼は飛距離やスコアや賞金といった数字ばかりを追いかけない。それらを「仕事」として追いかけざるを得なかったとき、彼は長尺パターを使ってきた。ところが最近になって、若い頃から愛用してきた短いパターに、あえて戻したという。
シニアツアーは、「同窓会」のようなものでもありますよね。初日のスコアがよければ優勝も考えるけど、そうでなければ皆でワイワイ(笑)。シニアはそれでいいと僕は思うんです。シニアにまでなって、そんなに真面目にやってどうするんだと。レギュラーのときにもっと一生懸命やっておけばよかったでしょって。
僕は20年くらい練習もしていません。もう、上手くなる必要がないから。たとえばこの鳴尾ゴルフ倶楽部に来ても、僕はプレーをしないんです。鳴尾のメンバーの方々と一緒に歩いて、おしゃべりして、レッスンして、自分は打たない。ゴルフはアマチュアのためのもの。僕はプロになっちゃったから、もうアマチュアには戻れない。だからプロとして、シニアツアーもそうですけど、皆が喜ぶために自分は何ができるのかを考えます。
東日本大震災の映像を、僕はアメリカのホテルで見たんです。それ以来、人間の幸福感について、かなり影響を受けたと思います。モノというのは、津波がさらって消えてしまうことをまざまざと見せられ、だったら何が幸せかと。父が09年に亡くなる間際、たまたま息子が帰国していて、死に目に会えたんです。それを思い出して、人がそばにいることって、幸せだよなと。
今、僕には再婚した妻と、その妻の娘と、娘の子が2人いて。つまり、僕には孫が2人できたんです。いい縁をもらえたなと思っています。幸せなのは、そうした人と一緒にいられるということですよね。
11年にはシニアツアーでたまたま勝っちゃったけど、だからといってそれほど嬉しくはなかった。僕、02年から20年間も長尺パターでしたけど、それはショートパットでドキドキしないために使い始めたんです。つまり、スコアのためにね。それが最近、短いパターに戻したんですよ。そうしたら、1試合で3パット6回(笑)。でも、なんかこれでいいんじゃないかなぁってね。ドキドキしながら、入ったり、外れたり。そのうち、もしかしたら、ゴルフが楽しくなるかもしれないでしょ。



98年のJCB仙台で93年に続く同大会2度目の優勝を果たしたが、その時手にしていたのが今も大切にしているゼブラパター。「悲喜こもごもを共にしてきた1本だね」
● ● ●
果実の皮でもむくかのように、水巻善典はパターのヘッドカバーを外して見せてくれた。
「クラブもモノでしかないから、僕はそんなに思い入れがないほうなのですが、コイツだけはなぜかそばに置いておきたいんですよ」
28年前から使っているというパターの黒いフェースには、中央にほんの小さな白い点があった。それは幾千幾万と彼が球に当ててきたことにより、そこだけ塗装が剥げてできた点。その古びたパターで最近は、彼の言う「同窓会」に臨んでいる。
「僕のゴルフは、最近始まったばかりなのかもしれないなって、思ってみたりもしています」
そう微笑みながら、彼はフェースの点を優しく親指でなでた。

月刊ゴルフダイジェスト2022年7月号より


 レッスン
レッスン ギア
ギア プロ・トーナメント
プロ・トーナメント コース・プレー
コース・プレー 書籍・コミック
書籍・コミック