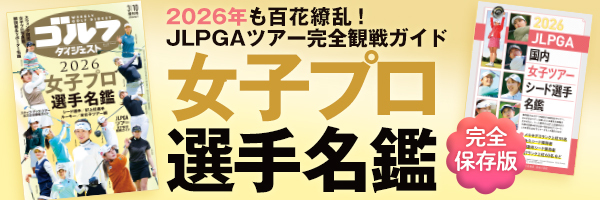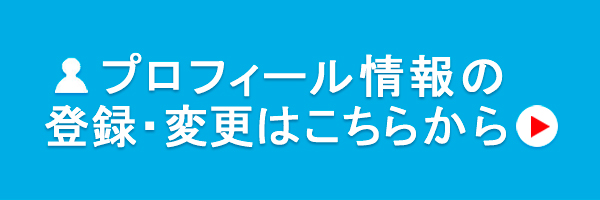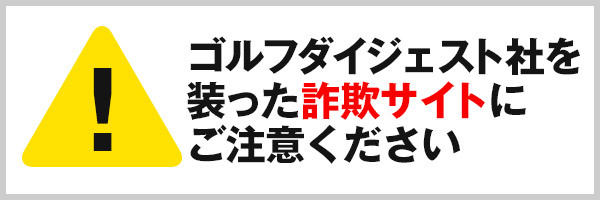【ターニングポイント】服部道子「私には“好転力”があったんです」
 ターニングポイント
ターニングポイント
服部道子がコロナ禍に初めて出版した書籍のタイトルは『好転力』。そのゴルフ人生は好転を求められる辛苦が多かった。鳴り物入りでプロになったものの長らく勝てず、賞金女王を目指したその年に父を亡くした。心の「感じ方」を変えることで好転させ、19アンダーという記録さえ生み出した、ターニングポイントーー。
TEXT/Yuzuru Hirayama PHOTO/Takanori Miki

「成績を出すことしか
他に方法がなかったんですよね」
可愛い子には旅をさせよ、とはいう。服部道子は、どれだけ両親に可愛がられた娘だったのだろう。
1984年に15歳9カ月の史上最年少(当時)で日本女子アマに優勝すると、翌年全米女子アマ出場。携帯電話もインターネットもない時代、高校2年生の女の子が単身渡米した。しかも同大会で日本人初の快挙となる優勝を遂げる。
高校卒業後はテキサス大学オースティン校に留学し、国際経営学を学びながらゴルフを続ける。帰国後、彼女を待っていたのは、母からの意外な言葉だった。
ゴルフは家族で楽しめるからと、祖父の好昭に勧められて始めました。小学校4年生のとき自宅より近い三好カントリークラブで開催の東海クラシックを観戦に行きました。そこで招待選手ナンシー・ロペスさんを偶然お見かけして、なんて素敵でカッコイイなぁって。医師だった父の弘道はそれまで転勤が多かったんです。ですがその頃、愛知県日進町(当時)という田舎町にちょうど開業して腰を落ち着けたんです。しかも私は幼い頃から体が弱かったので、激しくないゴルフならできるかなと。いろいろ重なっての、ゴルフでした。
ただ、私が始めた頃は周囲にゴルフをしている子どもがほとんどいなくて正直退屈でした。練習に夢中というより、自然が好きで練習をサボって虫を捕まえて遊んでいるような子どもだったと記憶していますね。。母の紘子(1962年日本女子アマ優勝者)も私にプレーを教えることはなく、野放し状態(笑)。母は父の仕事を手伝っていたので、娘にかまってなどいられなかった状態でした。
中学1年生からジュニアの大会に出場するようにはなったのですが、何もない小さな田舎町から違う土地へ行けるという、旅行感覚がありました。自分の世界を広げるためには、成績を出すことしか他に方法がなかったんですよね。全米女子アマの出場権を得られたときも、アメリカのピッツバーグへ一人で行きました。自由にやれるから気楽だなって、まさに怖いモノ知らず(笑)。決勝は日本で経験のない初めての36ホールのマッチプレーでした。相手はオハイオ州立大学の学生でお互いの技術を高め合うような試合になって、ずっと試合が続いたらいいのに、というぐらい楽しかったですね。
実家は病院に隣接していて、父や母が夜中に呼ばれることが多々ありました。次の日、患者さんがいたはずの病室に誰もいなくなっていて。ああ、亡くなったんだなと。小さい頃から人の死というものに接してきて、今やらないと、次はあるのかわからない、人生は頑張れるうちに頑張りたい、やれることはとことんやりたい、自然とそう思うようになりました。
大学はアメリカへ留学したのですが、勉強とゴルフの両立に必死でした。単位も落とせないし、ゴルフの成績も悪ければ奨学金を止められて日本へ帰される。在学中に日本に2回しか帰国せず、母が来たのも4年間で約1週間。国際電話が高いから連絡も取らず。そんな瀬戸際でしたけど、人間はなんとかやれちゃうものだなって思います(笑)。
卒業後は国際経営学を生かして商社にでも就職しようと思っていたら、帰国後に母が「プロテストにエントリーしておいたから」って(笑)。それまでプロになる気はなかったのですが、じゃあ、受けるだけ受けてみるねって。高校一年生の時からいろいろな国でプレーさせていただいた経験が生きて、その経験だけで合格(トップ通過)できたようなものですね。

日本女子アマを当時の史上最年少で優勝
高校1年生だった84年、15歳9カ月で日本女子アマを制した。この翌年には全米女子アマを当時史上最年少、日本人として初の優勝を果たした
「4年間のブランクで
“浦島太郎”状態。
周囲になじめず孤独でしたね」
2位以下はすべて敗者であるのなら、勝利よりも敗北が圧倒的に多いのが、ゴルフである。
全米女子アマ優勝で、鳴り物入りでプロデビューしたが、2年以上も勝てなかった。初優勝は1993年のミズノオープンレディス。雨中のプレーオフを制した裏には、プロ野球で3度「三冠王」を達成した落合博満との出会いがあった。
帰国してプロテストに合格すると、周囲から騒がれました。アメリカにゴルフ留学した選手なんていない時代でしたから、珍しがられたんでしょうね。でも私自身は地味な学生生活を送ってきただけで、プロとしての自覚がなにもありませんでした。4年間のブランクで「浦島太郎」状態(笑)。周囲になじめず孤独でした。
大学ゴルフ部で活躍し文武両道で賞を獲得
テキサス大学オースティン校に留学し、文武両道の学生に送られる「マリリン・スミス賞」を受賞
騒がれるのも好きじゃなく、目立ちたくもない。ゴルフに対してもポジティブになれずにいました。そんな心を勝負の神様が見ていて、だからずっと2位止まりだったのかなって思います。あるとき知人が落合博満さんとラウンドする機会をくださったんです。勝つためには何が足りませんか、なんて安っぽい質問もできず、ただ黙ってラウンドをさせていただきました。すると最後に、「苦手なことを続けなさい」と。
見抜かれているなと思いました。プロになってしまったからやる、ではなく、やると自分で決めたからには覚悟してやる。そうしなければゴルフに対しても、自分の人生に対しても、失礼じゃないかと。
当時はショートパットが苦手で、肝心な場面でも幾度も3パットしていました。決してパッティングを疎かにしていたわけではなかったのですが。ただこれだけ試合が多ければ、どこか得意なコースで勝てるときがくるという、甘い考えもありました。それじゃいけないと疲れていても毎日早起きし、苦手だったジョギングを始めました。ようやく自分の心と向かい合えた気がしましたね。
1993年のミズノオープンレディスでは、最終日の最終グリーンで、また3パットしてしまいます。プレーオフになったのですが、私がパーで相手がボギー。ツアー初優勝がついにやってきました。落合さんにお会いして3週間後のことです。いつも勝者に拍手を送っていた表彰式で、私の手にカップがあって。ああ、2位と優勝って、こんなにも違いがあるんだな、そう実感しました。もう、負けたくないと。
「あんな感覚は初めて。
本当にカップが
大きく見えたんです」
会心の試合、というのは、プロ中のプロといえども、生涯に幾度もないという。
「自分のスウィングがスローモーションだった」「観客のように冷静に試合を見られた」「カップが大きく見えて外す気がしなかった」。
1998年の伊藤園レディス。19アンダーという最小スコア世界タイ記録で優勝。その年の賞金女王を決められたのは、しかし、父を亡くした悲しみの直後だった。
1998年は、私自身ゴルフに手応えがあって、賞金女王を狙おうというシーズンでした。その4月に父が階段から落ちて足を骨折し、病院に運ばれました。そこで大腸癌がステージ4であることが判明し、余命2カ月と宣告されたんです。父は外科医だったので、病状を知っていたと思うのですが、父には告げないことを家族で決めました。父は私のゴルフを楽しみにしてくれていたので、私がゴルフをせずに付き添ってしまってはいけないと、試合に出続けました。
月曜日にお見舞いに行き、そこから試合に臨むのですが、不甲斐ない成績が続きました。そして宣告通り、6月の土砂降りの日、父は亡くなりました。自宅から一番近くの三好カントリークラブで行われる日本女子オープン前の日曜日でした。私は気持ちの整理がつかずに欠場を決め、約1カ月試合から離れました。
復帰後に2勝を挙げ、序盤の2勝と合わせて4勝し、迎えた伊藤園レディス。シーズン終盤で賞金女王の重圧がかかる一戦のはずなのに、「怖さ」がまったくなかったんです。上からだと触っただけでグリーンからこぼれてしまうほどの超高速グリーンなのに、外すなんて思いもしない。だって、父の死よりも怖いことなんて、あるわけないですから。「ゾーン状態」とは、このことなのかって。こんな状態は初めて。本当にカップが大きく見えたんです。終わってみれば2位に11打差をつけていて、この優勝で賞金女王を獲ることができました。だけど不思議とゾーン状態はあの週だけでしたね(笑)。

98年には年間5勝を挙げ自身初の賞金女王に
賞金女王がかかった終盤の伊藤園レディスで2位に11打差をつけてぶっちぎりの優勝。最愛の父の死を乗り越えての快挙だった
「何をするにしても
最後は自分自身。
ゴルフが私に教えてくれました」
これだけきっぱり引退してしまったトッププロはいるだろうか。
肉体に怪我はなく、年齢もまだ41歳。だがそこから新たな人生を歩み始める。引退前年、くしくも父と同じ職業、同じ名の医師と巡り合って結婚。引退後に息子を授かった。さらには東京オリンピック日本代表コーチとして、稲見萌寧の銀メダル獲得を後押しした。
トッププロとして、妻として、母として、そしてコーチとして。いつでも自分の人生を輝かせる、その「ワクワク感」とは?
41歳までゴルフを続けてきて、おかげさまで体には痛いところがひとつもなかったんです。でも心のどこかに、これ以上続けていてもどうなるのかな、もうゴルフはやりきったんじゃないかな、という思いがありました。そんなとき、母の先輩で私のことを小さな頃から知ってくれている当時70代の女性の方とプロアマでご一緒させていただき、こう言われたんです。「ゴルフも確かに素晴らしいけど、あなたはいつまでその白いボールを追いかけているの?」
長く続けてきたことをやめるのは勇気がいることです。ただ、プロになったときに覚悟が足りずに漫然とプレーしてしまった。ああいうことだけはしてはいけないと。何をするにしても最後は自分自身。ゴルフが私にそう教えてくれました。
引退してみると、それまでは自分がサポートしていただくばかりで、恥ずかしながら、お料理も、銀行での振り込みも、電車の切符を買うことさえもできなかったんですね。それだけにすべてが新鮮で、結婚や子どもができたことにも、また新しい人生が始まった「ワクワク感」がありました。当時のママ友には、私がプロゴルファーだったことを知らない人もいるんです(笑)。
東京オリンピックは、目標を持って頑張る若い選手の活躍するところを、私自身が見てみたかったんです。そこに少しでもお役に立てることがあればという思いでコーチをお引き受けしました。小さな頃からゴルフを一人でやってきましたけど、今になって思うのは、自分一人の力なんて微々たるもの。それはコーチも同じで、いろんな能力や考え方を持った人が、同じ目標を持って集まって、それぞれが力を合わせることが大切だなと。
稲見さんの銀メダル、あのラストのバーディラッシュは、もちろんご本人の頑張りです。だけど彼女の裏には、それまでたくさんのスタッフが準備をしてきたことを私は見てきました。そのみなさんと、やはり「ワクワク感」、「ドキドキ感」で、最後は稲見さんの結果を喜び合えたことに、感謝の気持ちでいっぱいになりました。



● ● ●
インタビュー前夜は雨だったが、「晴れ女」を自称する彼女らしく、東京の空には雲ひとつなかった。
オフィス街を並んで歩きながら、コロナ禍に出版された書籍『好転力』というその題について聞いた。
「コロナもそうでしたけど、苦しいとき、つらいときが、誰にでも必ず訪れると思うんです。そんなとき、何が状況を好転させるのかなって」
思えば、「晴れ女」のはずなのに大切な試合は、いつも雨だった。日本女子アマの初戴冠、プロ初優勝、そして、人生最後の試合も。
「雨であることを、どう感じるか。空模様だけを見たら、今日は雨で嫌だなぁって。だけど、感じ方を変えてみる。雨でもいいことないかなって。すると、傘に当たる雨粒の音さえ、愛おしく楽しめたりもするんですよね」
青空の下、笑顔で手を振り、ゴルフとは無縁の、夫と息子が待つ家へと、彼女は帰っていった。

月刊ゴルフダイジェスト2023年8月号より


 レッスン
レッスン ギア
ギア プロ・トーナメント
プロ・トーナメント コース・プレー
コース・プレー 書籍・コミック
書籍・コミック